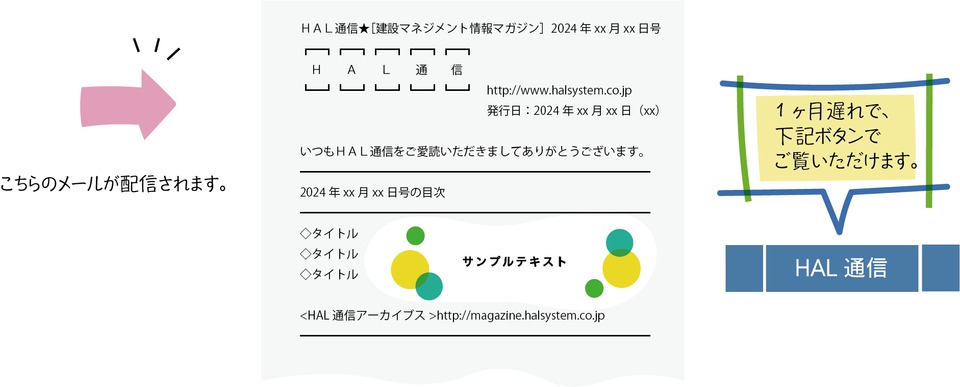靖国参拝を論ずる 第1回:特攻隊
2014.02.19
今回から数回に分けて、靖国参拝に潜む本質の問題を論じてみたいと思います。
第1回は「特攻隊」です。
第1回は「特攻隊」です。
百田尚樹氏の「永遠のゼロ」に対し、中韓はもとより、国内の護憲団体などからも批判が寄せられている。
「風立ちぬ」の宮崎駿氏などは、かなり激しい言葉で映画になった同作を批判している。
この小説は、誰もがご存知のとおり、特攻隊の悲劇を扱ったものである。
特攻隊と靖国とは深い関係にあることから、靖国批判が挙がる毎に逆の反発のボルテージも上がる。
それで今回は、特攻隊の問題を取り上げてみた。
特攻隊は、二つの側面を持つ。
ひとつは、死を命じられた(形の上では「志願」となっているが、実質は「命令」である)若き特攻隊員たちの「個人」としての悲劇である。
そして、もうひとつは、他国に例のない「必死」の作戦を「国家」が立案し、強制したことである。
海軍でも陸軍でも、特攻隊員たちは、みな正規の軍人である。
ゆえに、ここに大きな矛盾が生じてしまう。
個人としての特攻隊員たちは被害者であり、何らの責任もない。
だから、彼らの行為を無法、犯罪として糾弾することは、到底出来ない。
しかし、国家としての「特攻」は無法であり、国民に対する犯罪である。
しかも、その特攻を実際に実行したのは、彼ら「特攻隊員」たちなのである。
つまり、個人に重きを置けば、彼らの行為を「賛美」とまではいかなくても、その心情には同情を禁じ得ない。
しかし、一方でそのことが「特攻」という無法作戦に対する批判を弱めてしまうことになる。
他方、国家(旧帝国日本)に重きを置けば、「特攻」は犯罪として断罪すべき事実である。
だが、そうなると「特攻隊員」たちは実行犯になってしまうのか、という問題に突き当たる。
国内から見れば、当然、個人の悲劇としての側面が強くなる。
「永遠のゼロ」に限らず、大半の特攻隊ものの小説や映画は、その側面が色濃く描かれている。
しかし、海外から見ると、「国家の犯罪」という側面が強くなるのである。
まして、日本は「敗戦国」として、被告の扱いを今日でも受け続けている国である。
中国や欧米(ドイツ、イタリアを除いてだが)は、「戦勝国」としての自らの地位を永遠に継続したいと思っている。
日本における「特攻隊員への同情・賛美」は、それへの挑戦と写ってしまうのである。
そして、靖国神社がその「挑戦の象徴」として捉えられているのである。
日本国民としては、どうしようもない矛盾である。
私の伯父の一人は海軍特攻隊の生き残りである。
上京する時はいつもホテルニューオータニに泊まる。早朝、靖国神社に参拝するためである。
ある時、伯父に参拝するわけを聞いてみた。
伯父は、静かにこう説明してくれた。
「靖国神社を支持しているわけではないんだ。死んでいった連中と『死んで靖国で会おう』と誓い合った。あそこしか彼らに会える場所はないのだ」