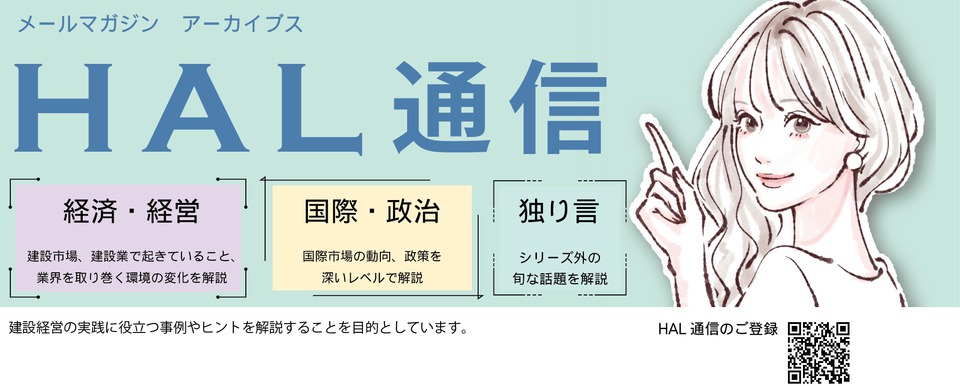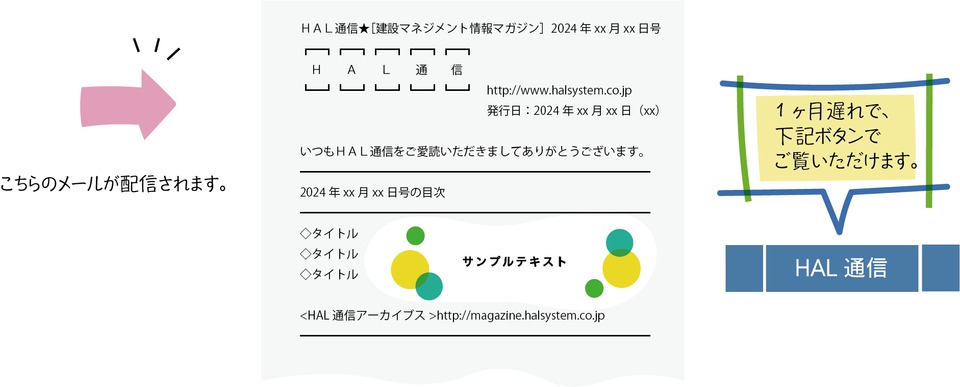中道改革連合
2026.02.16
「中道」という言葉は、もともと仏教用語で、創価学会のカリスマであった故池田大作氏が唱えていた「中道人間主義」に繋がる言葉で、創価学会色の強い党名といえます。
この党名について、立憲民主党の野田代表は「右にも左にも寄らない真ん中に位置するという意味です」と述べましたが、私の頭に浮かんだのは「イソップ物語の“こうもり”」で、「良いとこ取りを狙って」どこからも相手にされなくなるというイメージでした。
本日19日に新党の綱領が発表されましたが、まず打ち出したのが「生活者ファースト」という言葉です。
小池都知事が言い出し、最近は色あせした感のある「○〇ファースト」という言葉に、「古いな~」と、まず、そのセンスが落第点です。
発表では、「多様性の尊重」とかの聞き飽きた言葉が並んでいたので、それらは割愛します。
そして、「5つの柱」が続きましたが、これにも、たくさんの余計な言葉が付いていたので、以下のようにポイントだけに絞りました。
【第1の柱:持続的な経済成長への政策転換】
【第2の柱:新たな社会保障モデルの構築】
【第3の柱:選択肢と可能性を広げる包摂社会の実現】
【第4の柱:現実的な外交・防衛政策と憲法改正論議の深化】
【第5の柱:不断の政治改革と選挙制度改革】
この中に「包摂社会」という聞きなれない言葉がありました。
どうも以下のような意味のようです。
「英語で“social inclusion”=すべてを包含する社会:社会的に弱い立場にある人々も含めた市民ひとりひとりを対象に、排除や摩擦、孤独や孤立から援護し、社会(地域社会)の一員として取り込み、支え合う考え方のこと」
全体に「可能性」とか「現実的」といった修飾語が多く、“あいまい”でボケた印象です。
最大の論点である原発、憲法問題、消費税については、事前に漏れていた内容からは大幅に後退しました。
(1)原発政策は、「将来的に原発に依存しない社会」を目指すとした上で、「地元合意、安全性確認、避難計画の策定を条件に再稼働を認める」と「原発ゼロ」を掲げてきた立憲民主党に配慮した文言に薄められました。
(2)安全保障面は、「集団的自衛権」への言及を避け、「平和安全法制が定める存立危機事態における自国防衛のための自衛権行使は合憲」と、意味不明。
(3)憲法改正については、「立憲主義を堅持した上での“責任ある憲法改正論議の深化”」と、これまた意味不明。
(4)消費税については、「食料品の消費税ゼロ」+「恒久的にゼロにする方向」という文言で議論したようですが、「財源は新たな税・・」とは書けず、盛り込みを避けたようです。
このように、事前に聞こえていた「原発再稼働の推進と憲法改正」は、完全に“ぼかされ”ました。
これまで立憲民主党は「安保法制は違憲、原発ゼロを目指す」と強く言ってきたので、そこは立憲民主党が強く主張したようです。
もっとも新党ができても立憲民主党は消えるわけではなく、参院議員と地方議員はそのまま同党の議員として残るので、「安保法制は違憲、原発ゼロ」は、そちらで唱えるということのようです。
このような“お粗末”な新党結成が選挙目当てに過ぎないことは、国民の目にはお見通しです。
こうした“ごまかし”に日本のマスコミが肯定も否定もしない中、中国共産党は早々と「大歓迎する」との声明を出しました。
中国と公明党との太い関係が新党に受け継がれことを示す話で、気持ちの悪さは拭えません。
記者会見での野田氏、斎藤氏の表情を見て感じたのは、野田氏の無力感浮かぶ表情、そして斎藤氏の“うまくいった”感の表情に、この合併劇の真相が見えました。
この党名について、立憲民主党の野田代表は「右にも左にも寄らない真ん中に位置するという意味です」と述べましたが、私の頭に浮かんだのは「イソップ物語の“こうもり”」で、「良いとこ取りを狙って」どこからも相手にされなくなるというイメージでした。
本日19日に新党の綱領が発表されましたが、まず打ち出したのが「生活者ファースト」という言葉です。
小池都知事が言い出し、最近は色あせした感のある「○〇ファースト」という言葉に、「古いな~」と、まず、そのセンスが落第点です。
発表では、「多様性の尊重」とかの聞き飽きた言葉が並んでいたので、それらは割愛します。
そして、「5つの柱」が続きましたが、これにも、たくさんの余計な言葉が付いていたので、以下のようにポイントだけに絞りました。
【第1の柱:持続的な経済成長への政策転換】
【第2の柱:新たな社会保障モデルの構築】
【第3の柱:選択肢と可能性を広げる包摂社会の実現】
【第4の柱:現実的な外交・防衛政策と憲法改正論議の深化】
【第5の柱:不断の政治改革と選挙制度改革】
この中に「包摂社会」という聞きなれない言葉がありました。
どうも以下のような意味のようです。
「英語で“social inclusion”=すべてを包含する社会:社会的に弱い立場にある人々も含めた市民ひとりひとりを対象に、排除や摩擦、孤独や孤立から援護し、社会(地域社会)の一員として取り込み、支え合う考え方のこと」
全体に「可能性」とか「現実的」といった修飾語が多く、“あいまい”でボケた印象です。
最大の論点である原発、憲法問題、消費税については、事前に漏れていた内容からは大幅に後退しました。
(1)原発政策は、「将来的に原発に依存しない社会」を目指すとした上で、「地元合意、安全性確認、避難計画の策定を条件に再稼働を認める」と「原発ゼロ」を掲げてきた立憲民主党に配慮した文言に薄められました。
(2)安全保障面は、「集団的自衛権」への言及を避け、「平和安全法制が定める存立危機事態における自国防衛のための自衛権行使は合憲」と、意味不明。
(3)憲法改正については、「立憲主義を堅持した上での“責任ある憲法改正論議の深化”」と、これまた意味不明。
(4)消費税については、「食料品の消費税ゼロ」+「恒久的にゼロにする方向」という文言で議論したようですが、「財源は新たな税・・」とは書けず、盛り込みを避けたようです。
このように、事前に聞こえていた「原発再稼働の推進と憲法改正」は、完全に“ぼかされ”ました。
これまで立憲民主党は「安保法制は違憲、原発ゼロを目指す」と強く言ってきたので、そこは立憲民主党が強く主張したようです。
もっとも新党ができても立憲民主党は消えるわけではなく、参院議員と地方議員はそのまま同党の議員として残るので、「安保法制は違憲、原発ゼロ」は、そちらで唱えるということのようです。
このような“お粗末”な新党結成が選挙目当てに過ぎないことは、国民の目にはお見通しです。
こうした“ごまかし”に日本のマスコミが肯定も否定もしない中、中国共産党は早々と「大歓迎する」との声明を出しました。
中国と公明党との太い関係が新党に受け継がれことを示す話で、気持ちの悪さは拭えません。
記者会見での野田氏、斎藤氏の表情を見て感じたのは、野田氏の無力感浮かぶ表情、そして斎藤氏の“うまくいった”感の表情に、この合併劇の真相が見えました。