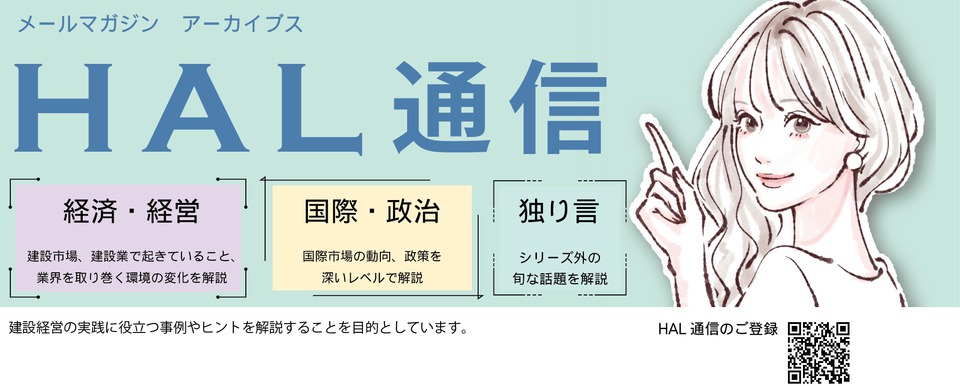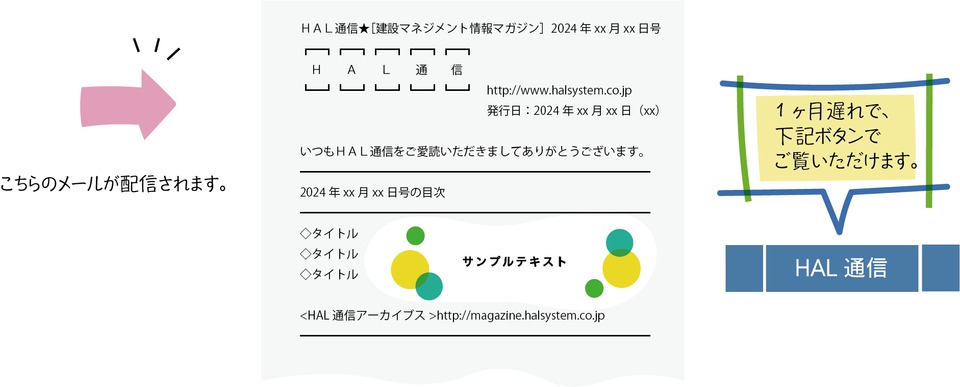USスチール買収問題(中編)
2025.07.16
急転直下、トランプ大統領の承認で、日本製鉄によるUSスチールの買収が決まりました。
この買収成立は、想定内とも言えるし、想定外とも言えます。
USスチールはもはや自力更生は不可能で、どこかに買収してもらう以外の道はありませんでした。
その買収に、日本製鉄と米鉄鋼大手クリーブランド・クリフスが名乗りを挙げましたが、クリーブランド・クリフスの買収提示額は火事場泥棒ともいえる低い金額でした。
経済合理性からいえば日本製鉄を選ぶのは当然で、経営陣だけでなく労組も日本製鉄を希望しました。
しかし、上部団体の全米鉄鋼労働組合(USW)は、日本製鉄による買収に反対しました。
USWは民主党の支持団体なのでバイデン前大統領も「日本製鉄はダメ」と妨害しました。
両者は、日本製鉄の子会社となるUSスチールが自分たちのコントロールから外れることを恐れ、選挙に影響することを恐れたわけです。
トランプ大統領も当初は反対していましたが、一転して「本社移転や工場の閉鎖は認めない」の条件付きで「計画的なパートナーシップ」という意味不明な言葉で承認に転じました。
この言葉はともかく、彼が承認することは早期に想定できました。
当時はあまりニュースになりませんでしたが、トランプ氏は就任直後にそれまでの完全不承認の立場を翻していました。
彼は、内政も外交も口だけで、実質的な策がなく、どこかで花火をぶち上げる準備をしておく必要に迫られていたわけです。
現在、USスチールの従業員は1.4万人ですが、「これで少なくとも7万人の雇用を創出し、米経済に140億ドル(約2兆円)の経済効果をもたらす」との相変わらずの大風呂敷も、嬉しさ百倍の現れで、実に分かりやすい人物といえます。
しかし、日本製鉄からの技術供与を受けて高品質の鉄鋼を生産ができるようになるのは1年では無理で、2~3年は掛かると思われます。
その効果で生産量が劇的に増えなければ大幅に雇用を増やすことは不可能ですが、トランプ氏は、輸入する鋼材に天文学的な関税を掛け続ければ、可能だと計算したのです。
と、ここまでは想定内でしたが、想定外のこともいろいろありました。
まず、トランプ大統領が、日本製鉄がUSスチールの株100%を持ち「完全子会社にする」ことを承認した点が挙げられます。
日本製鉄が過半数を持てるかどうかがカギと思っていましたから、これは意外でした。
前々から、大統領府が「黄金株」を持ち、最終決定権は米国側にあると主張していましたが、その中身が不透明でした。
結果は、大統領府が1株の黄金株を持ち、本社移転や工場閉鎖、従業員の解雇などを阻止する強制権を持つとされました。
つまり、黄金株の権限は、上記の移転や閉鎖、従業員の解雇を阻止することに絞られているわけです。
それでも、トランプ大統領は米国民に対して、「USスチールは日本製鉄に部分的に所有されるが、米国によってコントロールされる」と、強気の(苦しい?)弁明をしています。
たしかに、米国にはない「高級鋼製造技術」を持つ日本製鉄とUSスチールの「パートナーシップ」が米国民に与える心理的効果は、日本人が想像する以上にあります。
トランプ大統領は、中国を米国の最大の脅威とみなしています。
鉄鋼の過剰輸出問題はもちろん、いつか必ず紛争に発展する中国に勝つためには、兵器や艦船、軍用機などに必須の高給鉄鋼の確保がどうしても必要でした。
「鉄は国家なり」はあまりにも有名な格言ですが、鉄鋼業再生なくして米国の再生(MAGA)はない。
ゆえに、この買収承認の拒否はそもそも不可能でした。
さらに、「米国経済の再生を妨害しているバイデン前大統領の不承認」をひっくり返すという政治的な効果という側面もあります。
一方、日本製鉄側から見ると、USスチールの収益の全てが得られ、さらにUSスチールの役員の選任・解任に関する決議を単独に近い形で決める権利を手中に収められる。
つまり、経営をほぼ完全に支配できるということになります。
この点は重要で、日本製鉄はUSスチールに供与する「最先端技術の流出」などの不測の事態を防止できることを意味します。
ただ誤算もあります。
この買収で、現在世界4位の生産量を3位に上げられると見ていましたが、どうやら第4位のままのようです。
そのくらいUSスチールの業績は悪化していたのです。
ゆえに、同社の業績が上がり、さびれた中西部ラストベルトの「忘れられた人々」の生活を改善することに、トランプ政権は全面的な支援を行うはずです。
それで、目論見通り、第3位に浮上できたら、本当に「win-win」と言えるでしょう。
この問題の側面を、次回、もう少し深掘りしていきます。