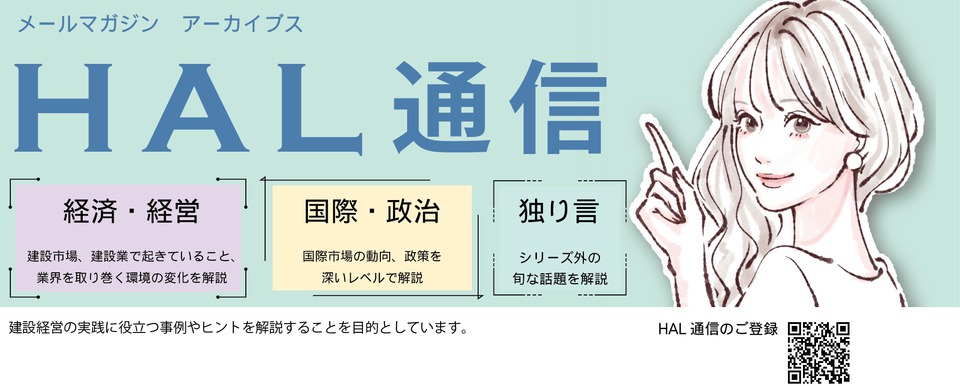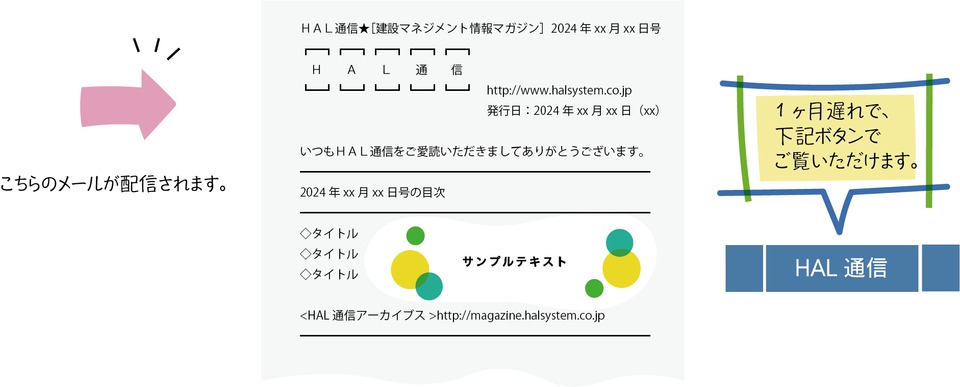米国の政治事情
2025.11.17
ニューヨーク市長選で、民主党の急進左派に属する34歳という若さのゾーラン・マムダニ下院議員が当選したのには驚きました。
同じ日に行われたニュージャージー州とバージニア州の知事選においても民主党が勝利し、1年前の大統領選の惨敗で分裂状態に陥っていた民主党が、急進左派を中心にまとまりつつあると分析されています。
一方の共和党は、トランプ大統領の暴走気味の政治に懸念を示す米国民が増えていることに危機感を抱き出していますが、自党の大統領を否定するわけにもいかず、沈滞ムードになっています。
こうした動きが、来年2026年の中間選挙にどう影響するかが注目されています。
日本でも急激に主役になってきたSNSを通じた若者の政治参加が、米国ではより早く大きくなり、今回のゾーラン・マムダニ氏のニューヨーク市長を生んだと分析されています。
私にしても、マムダニ氏についての情報は皆無だったので、急いで調べました。
分かったのは 「アフリカ・ウガンダ出身のインド系移民でイスラム教徒」という大変な異色さです。7歳の時ニューヨークに移住してきて、2018年に市民権を得たとなっています。
ということは、市民権を得て、わずか7年でニューヨーク市長ですから、驚きです。
マムダニ氏は、自身のことを『民主社会主義者』だと名乗り、自身と同じ移民や低所得の若者には高くて手が届かないものになってしまったニューヨークを、もう一度、市民の手に取り戻すことを選挙戦で掲げていました。
かつて大統領選に出馬したバーニー・サンダース上院議員も自身を『民主社会主義者』だと自任していましたから、マムダニ氏は、高齢の彼に代わる後継者のような位置付けになると思われます。
サンダース氏の支持者には、ハリウッド俳優や多くのミージシャン、そしてラッパーたちなど多彩な面々で溢れています。
サンダース氏の集会ではサイモン&ガーファンクル、ジョン・レノン、デヴィッド・ボウイなどの有名アーティストたちの楽曲が流れるように、中高年層からも幅広い支持を集めています。
こうした層の多くが、今回のニューヨーク市長選ではマムダニ氏に投票したと言われています。
日本では、ニューヨーク市長は東京都知事のように思われがちですが、米国では、それよりもはるかに大きな存在といえます。
米国民のシンボルの1人として、時にホワイトハウスにも物を言える立場だと言われています。
米国メディアは「今、ニューヨークは『新しい時代が始まるかもしれない』という期待感に包まれている」と報道しています。
ウォール・ストリート・ジャーナルなどは『グローバル資本主義の中心地ニューヨークで民主社会主義者のリーダーが誕生した。34歳という若いマムダニの勝利は、『地方選挙がこれからの国政に影響していく』と最大限の賛辞を流しています。
長らく分裂気味だった民主党が、この『民主社会主義』という概念のもとにまとまっていくと、来年2026年の中間選挙での勝利になるかもと報じられています。
こうした報道のように、もし中間選挙で共和党が大敗するという事態になれば、高齢も相まってトランプ大統領は急速にレイムダック化するでしょう。
せっかくトランプ大統領に気に入られたような高市首相ですが、ここは冷静に状況を把握して、あくまでも日本の国益第一で、米国の各層と適当な距離感で付き合うことが必要なようです。