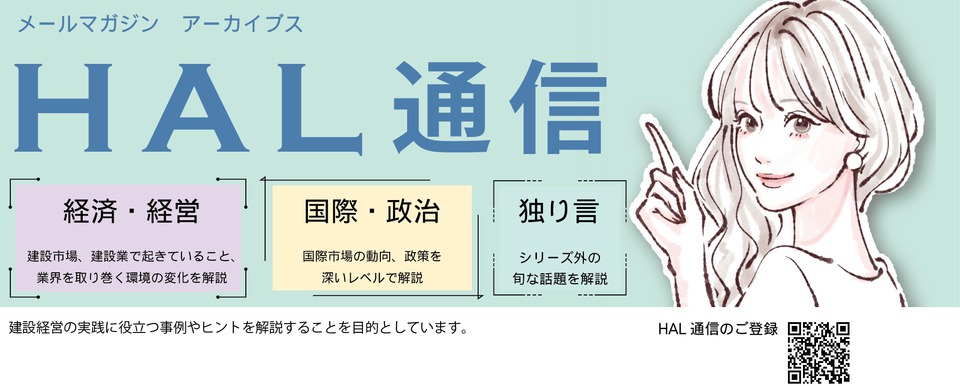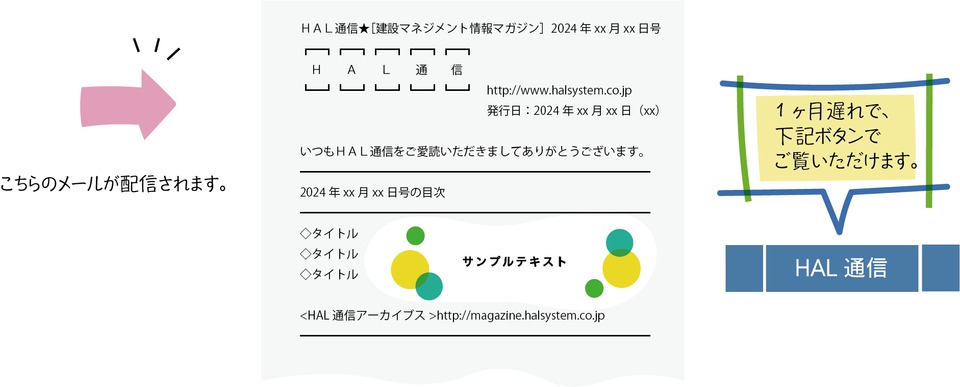2025年2月28日号(経済、経営)
2025.03.03
HAL通信★[建設マネジメント情報マガジン]2025年2月28日号
┏━┓┏━┓┏━┓┏━┓┏━┓
H A L 通 信
┗━┛┗━┛┗━┛┗━┛┗━┛ http://www.halsystem.co.jp
発行日:2025年2月28日(金)
いつもHAL通信をご愛読いただきましてありがとうございます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2025年2月28日号の目次
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇高関税という名のトランプ台風
☆水商売からビジネスを学ぶ(その7)
◇ホンダは日産ではなくソニーと手を組む道へ
<HAL通信アーカイブス>http://magazine.halsystem.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちは、安中眞介です。
今号は、経済、経営の話題をお送りします。
トランプ台風が吹き荒れています。
今号は、この話題から。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃◇高関税という名のトランプ台風 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
米国が世界一の国に“のし上がった”原動力は、2つの世界大戦です。
それまでの戦争は、ナポレオン戦争のように「野原で大軍がぶつかり合う」形態が主であり、稀に都市攻撃があった程度でした。
それが、2つの世界大戦では都市がターゲットとなり、工場や住居などの施設が廃墟と化しました。
こうして工業生産力を失った欧州や日本をしり目に、工場が無傷だった米国は、あらゆる商品や製品を湯水のごとく世界に輸出し、巨万の富を積み上げ、世界一裕福な国になりました。
このとき、極端な物資不足に悩む欧州・日本は、輸入する米国産品に関税を掛けることは、“もちろん”できませんでした。
結果、米国はこの無関税の「グローバリズムの恩恵」で、富を最大限に膨らますことが出来たというわけです。
それが今、トランプ大統領は、そのグローバリズムを否定し、極端なナショナリズムに走り、米国が輸入するあらゆるものに高関税を掛けると世界を脅しまくっているわけです。
その背景にあるのは2つの世界大戦後に米国に大きな富をもたらした製造業の衰退です。
今の米国製品は国内でも不人気です。
過去に黄金地帯だった中西部の工業地帯は、ラストベルト(rust belt=さびついた工業地帯)と称されるほど衰退しています。
トランプ大統領は、競合する外国製品に法外な関税を掛ければ、米国製品の競争力が上がって売れると主張して衰退地域の票を大量に獲得して大統領選挙に勝利しました。
しかし、関税は両刃の剣であり、米国が無傷というわけにはいきません。
そのためか、トランプ大統領は、各国が「相互関税」を掛け合うことを主張しています。
それは、以下のような理屈ではないかと推測します。
どの国でも輸入品に掛ける関税は、輸入国の「政府の収入」となります。
問題は「この関税は、いったい誰が支払うのか」ということです。
もちろん、支払うのは輸入国の消費者です。
ゆえに、消費の衰退を呼び、経済の下落を招きます。
しかし、国家は「政府の収入」となる資金を減税に回せば消費が喚起され、経済下落を防げるというロジックのようです。
これがトランプ大統領の頭の中の計算式ではないかと考えます。
では、果たしてこの計算式は成り立つのでしょうか。
成り立つのは、輸入国の消費者が「輸入品は高くなったので、国産品を買おう」と思う場合だけです。
自動車の購入を考えてみましょう。
25%もの関税が上乗せされれば、たしかに日本車は相当な値上がりとなりますが、米国メーカーはどうするでしょうか。
チャンスとみて、値上げに踏み切るのではないでしょうか。
その利益で収益の回収を狙うでしょう。
もちろん、値上げをせず、高くなった日本車からの乗り換えを期待するかもしれません。
しかし、日本車の良さやサービスに慣れた消費者が果たして米国車に乗り換えるでしょうか。
一部に「日本車は高くなったので、米国車を買おう」と、日本車を諦める消費者は出るでしょうが、結局、日本車に戻ってくると思います。
そのくらい、米国車の品質は低く、高燃費で、サービスは悪いです。
安さで売っている中国のEV車のほうが打撃は大きいでしょうが、それでも中国車も売れるでしょう。
バカ高いテスラなどの米国製EV車より、高関税がかかっても安いからです。
さらに、米国メーカーも大量の部品を輸入しているわけですが、それにも高関税が掛かるので、結局その分、米国車の価格も上がるわけです。
つまり、トランプ大統領の「関税政策」は失敗するということです。
しかし、ことはそう簡単ではないかもしれません。
現在、世界中でトランプ流の独裁思考の指導者が増え、国民の支持も増える傾向にあるからです。
その背景には、グローバリズムとナショナリズムの衝突が激しくなっていることがあります。
「グローバリズム=理想、ナショナリズム=現実」と置き換えてみると、よく分かるでしょう。
今の世界は「理想と現実がぶつかり合い、現実が優勢な」傾向になっているのです。
日本も「グローバリズム=理想」の進展で経済大国になった国です。
ゆえに日本は、ほとんどの輸入品に対し無関税か低関税としています。
しかし、例外があります。
それは、米(コメ)です。
農水省の関税率換算で778%という「えっ」というほどの高関税を掛けています。
ここだけ見れば、米国以上に“とんでもない”国です。
ところが、つい最近、農水省は、この見解を「280%」に修正しました。
これには、別の意味で「えっ」と驚きました。
このからくり、農政に詳しくない私には理解が出来ていません。
本メルマガの読者で、農政に詳しい方のコメントをいただきたいと思っています。
よろしくお願いします。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃☆水商売からビジネスを学ぶ(その7) ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
水商売の店を始めて2年目の暮れ、突然、水商売を取り締まる「風営法」が強化されました。
夜11時以降の酒類のみの提供および女性による接待の禁止です。
現在も、「夜10時以降、18歳未満の者に客を接待させる」ことは禁止されています。
(接待者を女性だけに限定していないのは、時代ですね)
この規制は強力に実施され、本当に夜11時過ぎになると、私のお店にも警官が回ってきて店内を見回りました。
さすがに“ビビった”近所の水商売のお店は、軒並み夜11時で閉店しました。
少しでも違反があると警察から警告が来て、度重なると営業停止という厳しさでした。
夜の繁華街は11時以降、火が消えたようになりました。
私のお店も同様でしたが、私は、この規制を逆手に取ることを考えました。
11時前にホステスを帰し、そこから業態を変えたのです。
私のバーテン助手を兼務していた一番古い女の子(この言い方を許してください)にはカウンター外での相手はさせず、服装も変えバーテン専業としました。
そして母の協力を得て、軽食の提供を始めたのです。
カレーライスやチャーハン、スパゲティ、おにぎりとみそ汁などの簡単なメニューを用意し、11時以降は、お酒と軽食の店にしました。
強化された風営法では、夜11時以降、お酒が主体の提供は禁止されましたが、「食事+お酒」の提供はOKだったのです。
しかし、競合店が出ることを想定し、他がマネできない奥の手を用意しました。
お米は新潟の米農家の親類から自家米のコシヒカリを仕入れ、味噌は知り合いの工場から直仕入するなど、徹底して本物の提供にこだわりました。
仕込みは母が行い、それを私ともう一人の女の子が引き継ぎ、提供するお店に変えたのです。
そうなってどうなったか。
他の水商売のお店は夜11時に閉まりますが、それで物足らないお客様を連れて、他店のホステスさんが私のお店に来るようになったのです。
彼女たちは、ウチのホステスではなくお客様ですから、連れてきたお客の相手をしても違法にはなりません。
私は、懇意にしていた喫茶店からコーヒーの回数券を買い、彼らが店を出るとき、ホステスに「ありがとう。これを使って」と、そっと渡したのです。
他店のホステスたちは、11時前から、入れ代わり立ち代わり私のお店に軽食を食べに来るようになりました。
そして、お酒も飲みます。
もちろん、彼女等のお客を連れてです。
私は、つくづく「男ってバカだな」って思いました。
馴染みになったホステスに至っては、店に入るなり、私にそっと「きょうは、何が余ってる?」と聞きます。
私が「ちょっと、カレーを作りすぎちゃって・・」と言うと、「まかせなさい」とウィンクして、連れてきたお客に「私、カレーが食べたい」と甘えた声で言います。
酔いが回っているお客は「いいよ、いいよ・・」と呂律の回らない口調で「バーテンさん、オレにも・・」なんて、いい格好をしたがる。
私は「ありがとうございます」と大きな声を上げ、安いカクテルを一つ「お口直しです」と言って出します。
中には、さらに良い格好を見せたいのか、「バーテンさんもお腹が減ってんだろう。好きなものを食べてよ」と羽振りの良さをアピールするお客もいました。
勿論、その分もお客様の支払いの中に“しっかり”と乗せていただきましたが・・
つまり、厳格になった風営法を逆手に取ったことで、店の売上は倍増、しかも自店のホステスは11時に返すので、人件費は下がる。
胸中ひそかに「笑いが止まらないな」と“ほくそ笑んで”いました。
いえ、決して、ほくそ笑んでいたわけではありません。
一家の生活費や自分の学費だけでなく、大学生になった弟、高校生と中学生の妹たち、合わせて4人の学費や小遣いもこの店の収益で賄っていたのです。
それこそ、必死の商売を行っていたことで、このような逆転発想が出てきたのです。
悪い事態が起きても、逆に考えれば良いことに転換できることが多いし、逆に良いことの裏には必ず悪いことが潜んでいます。
それに備えるという考えは、この時代に養われたように思います。
そして、その悪いことは、“必ず”起きてくるのです。
その話は次号で。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃◇ホンダは日産ではなくソニーと手を組む道へ ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
初代から7代に渡るスカイラインの開発で伝説の技術者となった桜井眞一郎氏は、最後まで「2000ccのエンジン」にこだわり続けた人でした。
高性能車のエンジンが2500~3000ccの時代になっても、桜井氏は頑なに2000ccから離れようとはしませんでした。
桜井氏は、このことを以下のように語っていました。
「車の性能を上げる一番簡単な方法はエンジンを大きくすることです。でも僕は2000ccの大きさの中で究極の車を作りたいのです」
私が7代目までスカイラインGTを乗り続けたのは、その桜井氏の哲学に“技術者の端くれ”として深く共鳴したからでした。
それゆえ、その桜井氏が日産を離れたとき、私もスカイラインから離れたのです。
そのときに感じた私の思いです。
「これで、スカGも“ただのファミリーカー”になってしまうな」
ホンダの桜井淑敏(よしとし)さんも、ホンダがF1から撤退したときに、「ホンダでの自分は終わった」と、役員の椅子を捨てて退社を決意したと、自らの口で語ってくれました。
そのホンダが日産と経営統合する話が浮上しましたが、すぐに決裂となりました。
当然だと思います。
生産台数が世界3位になること以外、ホンダにとって得なことが無いからです。
ホンダが考えていた合併の目的は、EV(電気自動車)の開発です。
車本体の性能においては、既にホンダは日産から学ぶものはなくなっています。
現在、主流となっているハイブリット技術は、トヨタが技術を開放していますし、ホンダも既に量販車を販売しています。
つまり、日産と組むメリットは無いのです。
一方、電気メーカーのソニーは、自社開発のEVで自動車産業に食い込もうとしていました。
しかし、車本体の技術は、ソニーといえども、そう簡単に取得できません。
また、量産体制を整備する工場の建設には莫大な投資が必要です。
ゆえに、手を組む自動車メーカーを探すのは当然の帰結です。
ホンダは日産と組むよりソニーと組むほうが現実のメリット、そして何より将来性が大きいといえるのです。
ホンダには、創業者の本田宗一郎が残した「二人三脚より一人で走った方が速い」という「一匹狼」の伝統がありました。
しかし、現在の三部敏宏(みべ としひろ)社長は、EV転換が進む先には「車のスマホ化」が進むとみて、それに対し1社で世界と戦うには限界がある、としています。
2年前には「スピード感を持ってホンダが描く将来性を実現するためには“ちゅうちょ”なくアライアンスを組む」と発言しています。
私は、60年近く車を乗り続け、かつ技術者の端くれでした。
経営者となった今も「オレは技術者だ」の意識は強いままです。
その経験から、現在はハイブリット車、次はPHV(プラグインハイブリッド車)が最適な選択だと断言できます。
BEV(バッテリーのみのEV)は、バッテリーが飛躍的に進化し、1回の充電で真冬や寒冷地でも1000km走行できるまでは買う気がおきません。
ということは、たぶん、運転できなくなる日までEVを買うことは無いでしょう。
----------------------------------------------------------------------
<編集後記>
フランスで流行っているというSNSアプリのBeRealが問題になっています。
最初に2分間だけアプリから画像が表示されるので、その間に自分の画像を送ると、ミックスされた画像が作られるという“らしい”のですが、大流行りとなっているそうです。
夢中になった子供たちが、授業中でも食事中でも熱中するので、社会問題となっています。
※お知らせ1
先月号で、新たに始めた新しい連載サイトを紹介しました。
「儲かる建設会社になろう」で検索してみてください。
建設関係以外の方も参考になると思いますので、ぜひ、覗いてみてください。
※お知らせ2
「責任あるAIってなんぞや?」のサイトは、4月から立ち上げる予定です。
そちらもぜひ、ご覧ください。
----------------------------------------------------------------------
◎[PC]配信中止、変更の手続きはこちら
http://www.halsystem.co.jp/mailmagazine/
このメールは送信専用です。お問い合わせはこちらからお願いします。
http://www.halsystem.co.jp/contact/
∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵
【編集・発行】
株式会社ハルシステム設計
http://www.halsystem.co.jp
〒111-0042 東京都台東区寿4-16-2 イワサワビル
TEL.03-3843-8705 FAX.03-3843-8740
【HAL通信アーカイブス】
http://magazine.halsystem.co.jp
【お問合せ・資料請求】
email:halinfo@halsystem.co.jp
tel:03-3843-8705
Copyright(c)HAL SYSTEM All Rights Reserved.
∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵