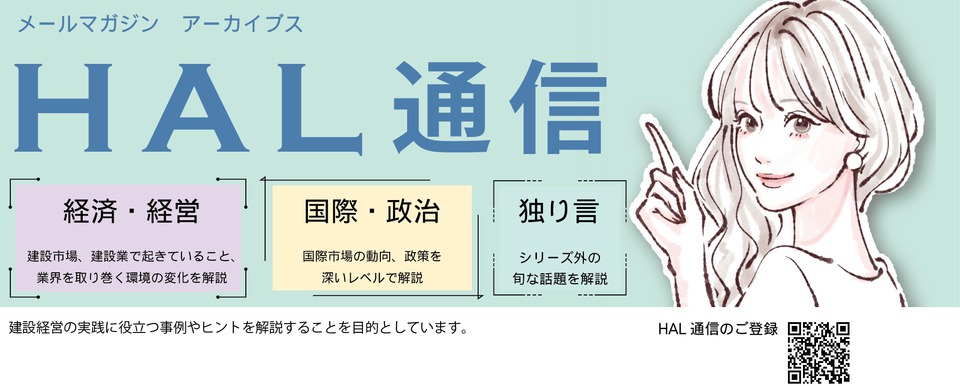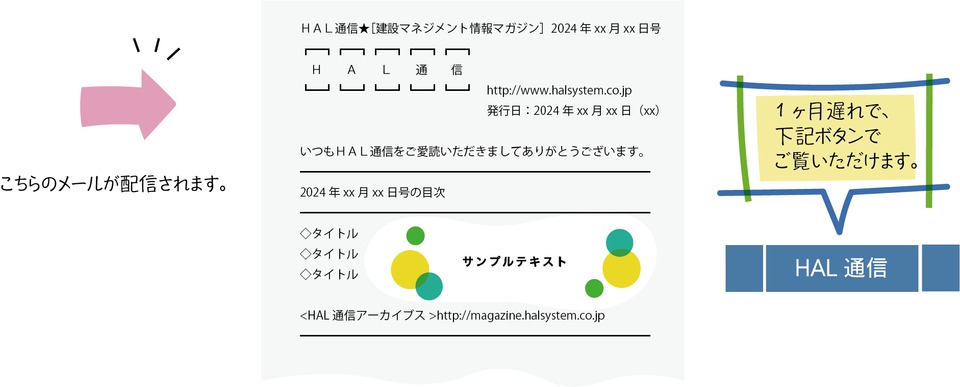2025年10月15日号(国際、政治)
2025.10.16
HAL通信★[建設マネジメント情報マガジン]2025年10月15日号
┏━┓┏━┓┏━┓┏━┓┏━┓
H A L 通 信
┗━┛┗━┛┗━┛┗━┛┗━┛ http://www.halsystem.co.jp
発行日:2025年10月15日(水)
いつもHAL通信をご愛読いただきましてありがとうございます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2025年10月15日号の目次
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇自公連立の終焉
◇働き方は、人それぞれが当たり前
◇中東に平和は来るのか?
<HAL通信アーカイブス>http://magazine.halsystem.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちは、安中眞介です。
今号は国際問題、政治問題をお送りします。
現在の政局は“すったもんだ”の混乱の中にあります。
今号は、この話題から入ります。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃◇自公連立の終焉 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
公明党の連立離脱が、日本の政治が26年間の硬直状態から脱却する第一歩になることを期待します。
これが斎藤代表の決断ではなく、高市政権を阻止すべく、バックにいる宗教団体と中国の指示であることはバレバレです。
チャンスとみて、立憲民主党は野党勢力による連立を呼び掛け、国民民主党の玉木代表を担ごうとしています。
それを受けた格好で、玉木代表は「総理になる覚悟はある」と発言しましたが、相変わらずの口の軽さ(腰も軽いですが)に、「有頂天になってんじゃねえよ」と言いたいです。
玉木代表は優れた方ですが、国家のトップになる器量は、まだまだ半人前です。
野田代表の口車に乗ったら、政権の運営はすべて立憲民主党に奪われ裸の王様になるだけです。
慎重派の榛葉幹事長が止めて、この目論見は霧散すると思いますが、どうなるでしょうか。
そもそも、民主国家の主権は国民にあります。
今の状況下では、国民の多くは、どんな組み合わせであれ、妙な連立政権など望んでいません。
各党は頭を冷やし、各党単独の力で総選挙に臨み、国民の信を問うべきです。
その前提でいけば、21日の臨時国会での首班指名は、各党の自由投票となり、決選投票で高市氏が総理になる確率が高いでしょう。
しかし、新政権は少数与党になるので、高市氏は早い段階で衆院解散に打って出るでしょう。
その結果を今から言うのは「どうかな」と思いますが、自民は増になり、国民と参政は大幅増、維新と“れいわ”は現状維持でしょう。
ただし、国民と維新は、妙な策略に乗った場合は減となるでしょう。
一方の立憲は大幅減となり、公明、共産も減、社民党は消滅同然を予想します。
だから、立憲民主党は今のうちに数合わせの政権奪取を目論んでいるわけです。
立憲民主党は、共産党やれいわ新選組にまで結集を呼び掛けていますが、数合わせというより「数遊び」に夢中になっているようにしか見えず「嘆かわしい」としか言いようがありません。
さらに公明党にまで呼び掛けている「節操の無さ」には言葉もありません。
政局の混乱は、次の総選挙まで収まらないでしょう。
今の厳しい状況を乗り切る力があるか否か、高市氏の力量を測る良いチャンスだと思います。
もちろん厳しい道ですが、トップに就任するということは、厳しいのが当たり前です。
中小企業でさえ、新たにトップになることは大変な重荷を背負うことになります。
まして、国家のトップですから、民間企業の比ではありません。
その意味で、本当にその覚悟を決めているのが誰かを国民は見ています。
この先、どのような政権になるとしても、ひとまず国土交通大臣の椅子が国民の元に戻ることは良いことです。
自公連立時代の26年間は、平成から令和と続いた経済の停滞時期と重なります。
国家としてのインフラ整備や国土開発は、国民の生活基盤や産業活動の基盤を創り維持する大事な仕事です。
そのかじ取りが公明党に握られていたことが経済停滞の要因の一つでした。
これで、ようやく本来のインフラ整備や国土開発のスタートに立てるということです。
必ず襲来する大地震だけでなく、毎年被害を出す台風や大雨に対する備えが進まないのも国交大臣のポストが宗教勢力と中国の影響下にあったことと無縁ではありません。
次がどんな政権になろうとも、このポストは国民のためにあることを貫いて欲しいものです。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃◇働き方は、人それぞれが当たり前 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
高市総裁の「馬車馬のように働く」という表現を巡って、マスコミや評論家たちだけでなく、SNSでも議論になっています。
この発言を巡ってテレビ番組などで、働き方や多様性の観点から様々な意見が寄せられています。
ユーザーコメントでは、「国のトップがそのようなことを言うと、国民への強制力になってしまう」という批判と、逆に「多様な価値観の働き方を認めるなら、馬車馬のように働くスタイルも多様性の一つとして認めるべきだ」という意見があり、さらに「比喩的な表現を過剰に批判するのは本質を見失っているのではないか」といった声も聞かれます。
このように、「ワークライフバランス重視の風潮+ハードワークを否定する」空気と、「高市発言はあくまでも個人の意見であり、自民党議員に対する檄だ」とする意見がぶつかり合っている印象です。
こうした議論、高市氏以外の他党の党首はどう思っているのでしょうか。
私の耳目には何の意見も聞こえず見えずですが、「余計なことは言わぬが花」なのでしょうね。
そもそもワークライフバランスとは何なのでしょうか。
現在、経営者である私は馬車馬のごとく働いていますが、サラリーマン時代も同じでした。
20代前半はスポーツ活動の比重がそれなりにあり、セミプロみたいな存在で仕事以上に馬車馬となり、ついには重い怪我を負い、選手生命を失いました。
でも、すべては自己責任です。
仕事でも、建設現場の事故で大きな怪我を負いましたが、監督である以上、それも自己責任です。
すべては個人の選択であり、馬車馬のごとく生きることも、逆に気楽に生きることも、批判すること自体“おかしい”と思うのです。
問題になるのは、そうしたハードワークを強制された場合であり、それには法的処置を含めた歯止めが必要です。
高市総裁の馬車馬発言は、もちろん強制ではなく自主的活動ですから、外野がとやかく言うことでは無いと思います。
今年はノーベル賞受賞者が2人も出て盛り上がっていますが、お二人とも、若い頃から本当に長い間、馬車馬のごとく頑張ってこられた方だと思います。
お二人以前の受賞者の皆様も全員、血のにじむような努力を長年続けてこられた方々です。
また、受賞の栄誉に到達できなかったけれど、同様の努力を続けた研究者や技術者の方も大勢いて、さらに名も無い多くの方の努力の上に今の日本の繁栄があります。
そのことを忘れたくないなと思います。
ただ、働き方の多様性や表現の方法および受け止め方についての活発な議論は大いにすべきです。
その過程で多様な働き方を認めるなら、馬車馬のように働く人もいて、適当に働く人もいて、なんもせずとも生きていける人がいるのが当然です。
批判のための批判が言いたくて、発言者の比喩的表現を切り取って批判するのは本質からずれているし、卑怯な気がします。
頑張っている人が評価される社会を願うだけです。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃◇中東に平和は来るのか? ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
2023年10月に起きたハマスによるイスラエルの音楽フェスへの襲撃テロから始まったイスラエルの怒涛の攻撃とハマスの反撃の応酬が約2年も続き、ガザ地方は6万人以上の死者を出し、住居の大半は“がれき”の山と化しています。
この状況の中で、イスラエルの猛攻を受けたハマスの主要軍事力はほぼ壊滅状態になっています。
こうした事態を見計らった米国トランプ大統領がイスラエルを促す格好でハマスとの停戦合意が成立しました。
このあたりのトランプ大統領の判断は的確といえます。
この合意でイスラエルの攻撃は止まり、ハマスによる人質20名が13日に解放されました。
しかし「第二陣で残る28名の人質の解放」と言われていましたが、すでに28名全員が死亡していることが判明しました。
その遺体を返還するとのことですが、遺体の状況は判明せず「全部は無理」との報道があります。
2年前の襲撃で拉致された人質は100名以上と言われています。
この先、イスラエル側で新たな怒りが起こることが懸念されます。
そうなると、逆にイスラエルに拘束されているパレスチナ人の囚人の解放がスムースに進むかが懸念されます。
仲介者のようになったトランプ大統領は鼻高々に「ガザでの戦争は終わった」と述べました。
しかし、これで本当にガザが平和になるかというと、そうはいかないでしょう。
双方の恨みは深い怨念となって残り、火種はくすぶり続けます。
すでにハマスはイスラエル軍が駐留していない地域に戻りつつあり、再び統制を取り戻しつつあると報道されています。
また、南部地域では「人民軍」と呼ばれているハマスに対抗する組織があると言われています。
イスラエル軍がこの「人民軍」を支援しているとの報道もあり、事態は複雑化の様相を強めています。
停戦の継続を監視するための国連軍の派遣が望まれますが、常任理事国が1国でも反対すれば組織することが出来ません。
ロシア、中国がトランプに歩調を合わせるはずもなく、それは夢物語に過ぎません。
米国が単独、あるいは欧州を引き入れて停戦監視軍を組織するとの報道が出ましたが、米国政府は否定しています。
昨年の春の停戦も、すぐに崩れてしまいました。
ゆえに今回も、このまま平和になると思っている人は少ないのでは・・。
イスラエルには自制を続けて欲しいものですが、そもそもの事を起こしたのはハマス側であり、ネタヤ二フ政権にとっては「ハマスの殲滅しか道はない」という意識に変わりはないと思われます。
少し前に、トランプ大統領が猪突に「パレスチナ人150万人をエジプトなどに移住させる」という案を出しましたが、賛同する国はありません。
移住先として名指しされたエジプトなどは即座に「No」を表明しました。
この案は、トランプ大統領の娘婿のクシュナー氏がイスラエルのネタヤニフ首相との会談で提案したと言われていますが、中東問題を自分の商売に利用する気持ちが露骨過ぎて、反発を生んでいます。
しかも、住民を移住させた後のガザ地区を「高級リゾート地」に造り変え、大統領引退後の大儲けを企んでいるとまで言われています。
トランプ大統領本人が、そこまでは言っていませんから、フェイクニュースの範疇を出ませんが、「あり得るかも」と思わせてしまう危うさを感じさせてしまっています。
あまり品がよくありませんが、こんな言葉があります。
「肥溜めの蓋をどんなに綺麗に磨いても、中身は“くさいもの”が詰まっている」
どんなに蓋を磨いて綺麗にしても(要するに、国家が法律や規則を整えても)、中身は糞尿という“くさいもの”が詰まったままであるという意味です。
つまり、「糞尿を浄化しない限り(国民の意識を変えない限り)、中身(国家)は綺麗にはならない」ということです。
中東は、2000年以上に及ぶ人々の怨念が詰まったままの状態です。
世界中の国が一致協力して、この糞尿自体を浄化しない限り、平和が来ることは無いのです。
こんな言い方をしてはいけないのでしょうが、簡単には打開策が思い浮かびません。
その意味では、荒唐無稽なトランプ案も一考の余地があるのかもしれませんが、とても賛同を得ることは無理ですね。
さらに2000年の時が流れ、世界が統一される日まで、この地に平和は来ないかと考えると、思考が停止してしまいそうです。
----------------------------------------------------------------------
<編集後記>
立憲民主党の安住幹事長が「首班指名は、しょせん数合わせだ」と発言しました。
政権が取れるかもと、気分が高揚しているのでしょうが、ずいぶんと国民をバカにした発言だと思いました。
国民は、数合わせの政権など望んでいません。
政治理念の整合性こそが、連立の最も大事な要素です。
公明党の離反で浮足立つ自民党議員ともども消えて欲しい人です。