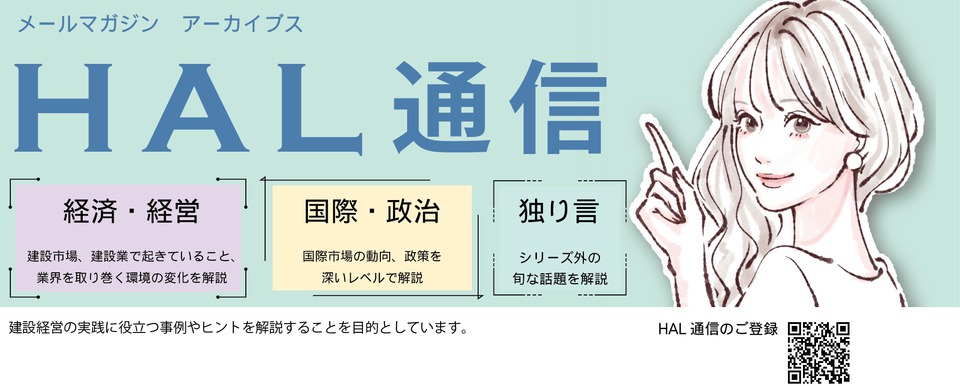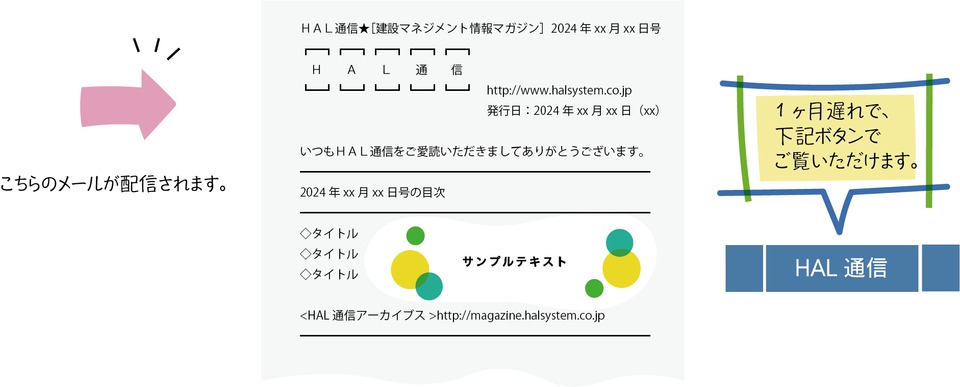2025年8月16日号(国際、政治)
2025.08.18
HAL通信★[建設マネジメント情報マガジン]2025年8月16日号
┏━┓┏━┓┏━┓┏━┓┏━┓
H A L 通 信
┗━┛┗━┛┗━┛┗━┛┗━┛ http://www.halsystem.co.jp
発行日:2025年8月16日(土)
いつもHAL通信をご愛読いただきましてありがとうございます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2025年8月16日号の目次
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇“やっぱり”な結果しかなかった米ロ会談
◇台湾有事の現実性
◇トランプvs DEI(その3)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちは、安中眞介です。
今号は国際問題、政治問題をお送りします。
今号は、15日に行われたアラスカでのトランプ・プーチン会談の記者会見を見てから原稿を書いていますので、1日遅れの8月16日号とさせていただきます。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃◇“やっぱり”な結果しかなかった米ロ会談 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
「今の時代、さすがに全面的な軍事侵攻はないだろう」との見方は、およそ3年半前のロシアによるウクライナ侵攻で破られてしまいました。
そして、一度侵攻に成功してしまえば、侵略した側が撤退することはまず無いという現実に世界は直面しています。
その現実はもう3年半も続き、今なお収束の気配はありません。
そうした膠着状態の中、米国トランプ大統領の突然の呼びかけで、米アラスカ州アンカレッジにおいて、トランプ・プーチン会談が行われました。
お互いを誉め合う“気色悪い”記者会見でしたが、互いの置かれた状況と思惑が透けて見えました。
ニュース解説者も言及していましたが、トランプは本気でノーベル平和賞が欲しいようです。
そして、どんな形であれウクライナ停戦を実現すれば、当然もらえると思っています。
しかし、ノーベル賞の推薦期限が9月末に迫る中、相当に焦っていたのでしょう。
それで、今回の対プーチン会談を皮切りに、ウクライナのゼレンスキー大統領を入れての3者会談で、強引にでも停戦を実現させようとしているわけです。
「中東のガザはどうでも良いのかよ」と言いたいですが、彼の辞書には「humanity=人道」なんて言葉はなく、「deal=ディール(取引)」と「self love=自己愛」しか無いようです。
記者会見を聞いた限りですが、何の新鮮味もなく、二人の爺さんが「互いを誉め合う」という気色悪い光景を見せられただけでした。
プーチンがこの会談に飛びついた背景には、破綻の淵にあるロシア経済の苦境があります。
この会談で西側の経済制裁を少しでも緩和させられないかという焦りを感じました。
頼みにしていた中国の支援がほとんど得られていないどころか、温暖化によって北極海航路を中国が開くかもしれないことを恐怖しているように感じました。
単にノーベル平和賞が欲しいだけのトランプに比べて、プーチンの立場が非常に悪いことを如実に感じさせる記者会見でした。
トランプは、ウクライナを入れての3者会談に言及していますが、会談自体は行われる可能性が高いと思われます。
この会談は「どちらが妥協するか」の問題になりますが、プーチンの妥協は考えられず、トランプがプーチンに肩入れしてゼレンスキーを脅す場面のほうが考えられます。
ただし、プーチンが要求する東部4州の放棄およびNATO加盟の断念などの条件をゼレンスキーが飲む可能性はほぼゼロです。
結局、トランプは「後は欧州が面倒見ろ」と投げ出すのではないでしょうか。
さすがに、そこまで言い切ることは無いでしょうが、投げ出す姿勢は見せるかもしれません。
こうした脅しに負けて欧州の腰が引け、結果としてウクライナがロシアに組み入れられるとしたら、次は欧州東側に位置する国々がロシアの侵略の餌食になることは確実です。
プーチンは、旧ソヴィエト連邦の復活を己の政治目標としていて、その野望を諦めることはないでしょう。
こうした身勝手なプーチンの夢が実現したら、EU東側の各国はロシアに削り取られ、世界情勢は一気に緊迫化します。
当然、EU(というよりNATO)はそうした事態を容認できないので、フランス、英国は言うに及ばず、ドイツもNATOの軍事強化に全力を挙げ出しています。
今のロシアにはNATOとの軍事衝突に勝ち切る力はないため、この策が最も現実的な策といえます。
一方、トランプは、以下のシナリオを考えている節があります。
ロシアのウクライナからの全面撤退は要求しない(それが当然なのですが・・)。
代わりに、現在の戦線での停戦、または一部地域をロシアの支配下に置く代わりに後の地域からのロシアの撤退を要求する可能性があります。
この場合、「一部地域」の線引きが非常に難しく、おそらく、クリミヤ半島およびルハンスク州とヘルソン州南部のロシアへの引き渡しではないかと思われます。
それでロシアが納得しない場合は、さらにドネツク州西部の引き渡しも付けるかもしれません。
しかし、ウクライナにしてみれば、どの案も到底飲むことが出来ずに拒否するでしょう。
となると、前述したように、トランプは投げ出し、「あとは欧州がやれば・・」と、同じシナリオとなります。
このように、関係国が納得できる結果が出ることはまったく期待できない会談を、なぜにトランプは持ち掛けたのでしょうか。
それは、前述したように「ノーベル平和賞が欲しい」の一点なのです。
最近の戦況ニュースを聞くと、前線はロシア有利に傾いているようです。
人口と武器・弾薬量で数倍の違いが大きいのですが、しかし、ロシアの兵站(武器・弾薬等の供給)能力はかなり落ちているようです。
ウクライナの戦う姿勢はなおも旺盛なので、この戦争を終わらせるには、米国がNATOと一致協力した軍事支援を強化してロシア軍の瓦解を導く以外の道はないように思います。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃◇台湾有事の現実性 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
7月に、陸上自衛隊が北海道で地対艦ミサイルの発射訓練を行いました。
国内での実射訓練は初めてということで、明らかに台湾有事を想定した訓練です。
防衛省は、日本周辺の情勢を「波高し」と言うべき状態にあると分析しています。
様々な識者がSNSなどで台湾有事のシナリオを解説しています。
共通しているのは、習近平国家主席の3期目の任期最終年となる2027年に侵攻を行うのではという見方です。
たしかに習近平主席は、憲法で「2期10年」となっていた主席の任期を、憲法改正して3期目に入っていますが、その改正理由を「台湾開放」と明言しています。
その期限が2027年なので、2年後が危ないと言われているわけです。
問題は、中国が2年後までに台湾進攻を行うだけの軍事力を整備できるかという点にあります。
現段階でも、台湾軍には単独で中国軍の侵攻を阻止できる力はありません。
しかし、中国が読み切れないのは、日本および米国の介入です。
もちろん、日米両軍が全力で台湾を軍事支援した場合、中国軍の敗北に終わる可能性が大です。
米国単独はもちろん、日本が単独で支援する場合でも中国軍の侵攻は難しくなるでしょう。
日本の石破政権は親中政権ですから、中国としては、この政権が長く続いて欲しいと思っているのは確実です。
おそらく一番の親中派と言われている岩屋外相を通じて、日本は介入しないようにと働き掛けをしているはずです。
ゆえに、自民党で一番強硬意見と言われる高市氏の登場は何としても阻止したいということです。
大事なことは、親中派であろうがなかろうが、「日本は武力による台湾進攻を許容しない」という明確な意志を内外に示すことです。
中国に対してそうした姿勢を強く打ち出せるのであれば、むしろ親中派政権のほうが有効といえるかもしれません。
そして、読みにくいのが、米国トランプ大統領の考えです。
中国は、大きなディールを持ち掛ければトランプ大統領が乗ってくるのかが全く読めていません。
最近、台湾の賴清徳総統の米国立ち寄りを拒否したように、トランプ大統領は台湾寄りとは言えないようですが、半導体王国の台湾を中国が手中に収めることを容認するとは到底思えません。
つまり、「軍事介入をしたくないが、中国が台湾を手中に収めることは容認しない」という考えだと思います。
さらに、トランプ大統領は「中国を世界経済の枠組みから排除しないと世界は壊れる」と思っている節があります。
こうした姿勢は中国側に伝わっていて、人民解放軍の弱腰に繋がっていると言われています。
近代の軍隊は、戦争を継続するための経済面を前面装備の充実以上に重視しています。
近代戦は完全な消耗戦になっていて、それを支える経済が崩壊しては戦闘の継続ができなくなっているのです。
こうした諸情報を重ね合わせて考えると、台湾有事の可能性は相当に低いと思われます。
ただし、戦争は偶発的な衝突から一気に拡大するという側面を持っています。
つまり、「引くに引けない」という事態です。
80年前の日本が、まさにそうした状態で「一か八か」の戦争に踏み切ったわけです。
陸軍将校だった父は、真珠湾攻撃の報に、同僚の将校たちと「なんてバカな」と言い合ったと語っていました。
日本は、中国の不安な思惑の目を丹念につぶしていく努力を続けていく必要があります。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃◇トランプvs DEI(その3) ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
しつこく書きますが、DEIはDiversity(多様性), Equity(公平性), Inclusion(包括性)の頭文字をとった言葉です。
まあ、「当たり前」のような言葉ですが、トランプ大統領は大嫌いなようで、米政府内で、この言葉を排除する姿勢が顕著になっています。
では、民間企業の対応はどうなのでしょうか。
この言葉が生まれた当時は「差別はいけない」という考えが広い支持を集めていたので、多くの企業は賛同の姿勢を明確にしていました。
ところが、平等姿勢に疲れてきて、DEI撤廃を発表する大企業が出てきました。
そうした動きは、トランプ大統領の就任以前にすでに動き始めていましたので、トランプが始めたことではないわけです。
ただ、大統領選と同時進行の形で企業に対するDEI廃止運動が行われ出してきたのは偶然ではなく、トランプの言動が大きく加速させたことは事実です。
こうした活動の旗手として米国で急速に名前を売ってきたのが、ロビー・スターバック・ニューサム(Robby Starbuck Newsom)という30代の人物です。
Wikipediaでは「アメリカの保守派の政治活動家、ミュージック・ビデオ監督、インフルエンサー」として紹介されています。
コロナの世界的流行の時、マスクとワクチンの義務化に強硬に反対したビデオで知名度を上げ、SNSでインフルエンサーとしての人気を上げていった人物です。
彼は、特に保守的な顧客を持つマクドナルドやウォルマートなどをターゲットにSNSでの批判や販売ボイコットなどを組み合わせた圧力をかけ、そうした企業にDEI廃止や一部撤廃に追い込むことに成功しています。
彼とトランプとの関係は直接ないとされていますが、政権の次席補佐官としてトランプとの関係の深いスティーブン・ミラーが設立した、「アメリカ・ファースト・リーガル」とは深い関係があると言われています。
その一方、アップルやマイクロソフト、コストコなどの比較的新しい企業は、これまで通りDEIを遵守すると宣言しています。
これらの企業は、多種多様な人種や女性を多く抱えてきたDEIの歴史が長く、顧客もグローバル的に幅広い層です。
そのメリットと社会的影響の大きさからDEI推進になっています。
今後さらに多様化するアメリカ、そして世界の中で、DEIにどう対応するかで企業の持つ価値観が評価され、その立ち位置が問われることになるのは間違いないでしょう。
かつてトランプは、飛行機事故が起きた時「機長が女性だから事故を起こした」と発言したことがあります。
この発言に対し、レポーターから「DEIが原因という根拠はあるのか?」と問われたとき、「自分には常識があるから」と答えました。
この答えには「白人男性が優れているのは常識だろう」というニュアンスが含まれています。
ゆえに、この発言に、他人種や女性に対する明らかな差別意識を嗅ぎ取ったという人が多いようです。
実際、共和党の中には「少数の優れた白人がアメリカを支配すべきだ」という過激な意見が根強く残っています。
白人が少数派に落ちる未来が現実に近づいてくるにつれて、そうした過激思想が表に出てきているという指摘もあります。
民主主義は、多数派の意見が優先されながらも、少数派の意見も保護される政治体制です。
それがもし少数派による支配になれば、世界に数多く存在する独裁国家のようになり、アメリカの民主主義は崩壊することになります。
そして、トランプのアメリカは一歩ずつ、そこに近づいているように感じます。
ちなみにトランプ政権の閣僚は2人を除き全員白人です。
(ルビオ国務長官はヒスパニック系白人です)
----------------------------------------------------------------------
<編集後記>
甲子園での高校野球が熱を帯びていますが、広島・広陵高校の途中での出場辞退という異常な事態も起きています。
暴力事案の発覚という事態に、「今の時代でも・・」という思いがします。
過去の高校での部活動の記憶の中に、こうした苦い思いを抱いている方もいると思います。
自分もその一人ですが、いつの時代でも暴力と人格を否定するような行為は許されるべきではありません。
しかし、教諭による盗撮事件などが出るたびに、指導者の資質が改善するどころか悪質化しているのではとの危惧を抱いてしまいます。
----------------------------------------------------------------------
◎[PC]配信中止、変更の手続きはこちら
http://www.halsystem.co.jp/mailmagazine/
このメールは送信専用です。お問い合わせはこちらからお願いします。
http://www.halsystem.co.jp/contact/
∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵
【編集・発行】
株式会社ハルシステム設計
http://www.halsystem.co.jp
〒111-0042 東京都台東区寿4-16-2 イワサワビル
TEL.03-3843-8705 FAX.03-3843-8740
【HAL通信アーカイブス】
http://magazine.halsystem.co.jp
【お問合せ・資料請求】
email:halinfo@halsystem.co.jp
tel:03-3843-8705
Copyright(c)HAL SYSTEM All Rights Reserved.
∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵