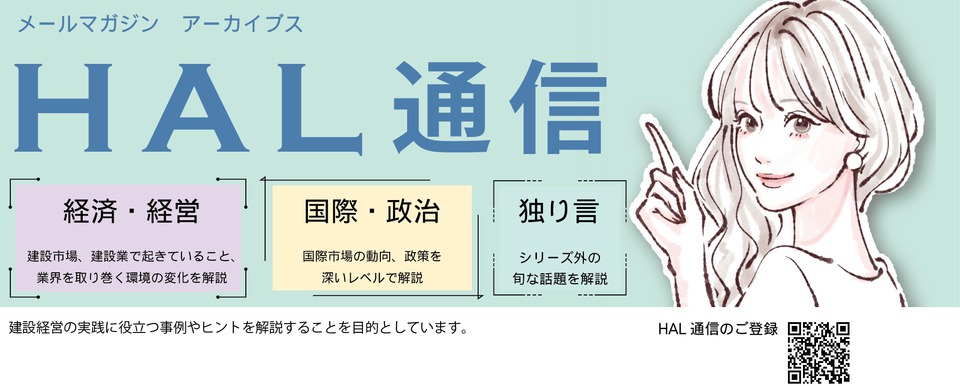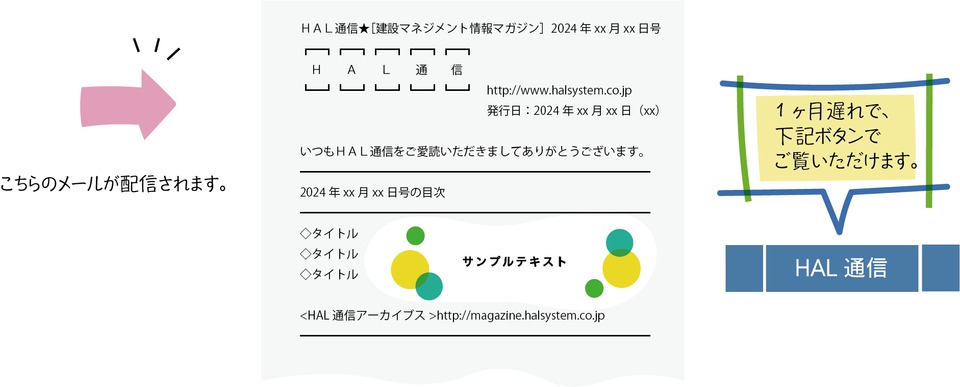企業の投資(2)
2025.08.01
参院選での党首討論において、石破首相は「消費税減税には断固反対」しか言わず、最も重要な成長戦略への言及は皆無でした。
野党からは、国民民主党と維新の党が「成長戦略が見えない」として非難しましたが、対案となる具体論がなく、選挙戦では成長戦略の議論そのものが乏しい結果に終わってしまいました。
つまり、与野党とも「成長戦略」を持っていないことを露呈した結果となり、日本全体の成長は望むべくもないなと感じました。
このような戦略なき国家運営に倣うかのように、企業の「成長戦略」の声も乏しいのが今の日本です。
新入社員確保のための「賃上げ」の声に比べ成長戦略の声はあまりにも“か細い”と言わざるを得ません。
「成長戦略」は、企業経営にとっては一番大事な、しかし一番難しいテーマといえます。
多額の投資を行い、成長を目論んでも、失敗すれば投資した金額が焦げ付き、下手したら巨額の債務だけが残るリスクが顕在化し、経営が傾く危険が大きくなるからです。
そのうえ、金融機関も投資家も、売り上げ維持と内部留保にしか興味を示しません。
投資に対しては懐疑的な見方のほうが強く、短期の出口戦略(つまり投資回収)にしか関心を示しません。
こうして政府および経済界全体が「現状維持」を続けた結果が「30年のデフレ」だったわけです。
たしかに、国内的にはそれで「可もなく不可もなし」としてバランスが取れていたわけですが、
ゼロ成長を30年も続けた結果、諸外国の成長に対し大きく後れを取ってしまい、国際競争力を失う危険の淵に立たされて、ようやく「これではアカン」と気が付いたわけです。
しかし、「現状維持」という環境に甘えてしまった経営者は、賃上げせず、研究開発も販売増進活動もせず、少ししか出ない利益を内部留保として貯めておくだけの経営に慣れてしまったのです。
その結果、日本国全体の地盤沈下が進み、ようやく慌て出し始めたのですが、成長戦略への投資を思い切って踏み出すことに、まだ躊躇があり、景気を押し上げる力は弱いままです。
そこには、大きな要素への理解が欠けています。
ここ数年、ようやく賃金が上がってきましたが、物価の上昇に追いつかない程度の賃上げで、経済全体を押し上げる力強さに欠けています。
それは、相変わらずベースアップという春闘型の横並び政策での賃上げだからです。
経済全体を押し上げるには、人員の移動や整理といった構造改革が必要です。
そして、それは労働組合主導の春闘型の賃上げでは不可能なことです。
30年のデフレの間に最も進化したのは、ITやネットです。
この理解や扱いによって、個々の従業員の生産性には大きな差が生まれています。
50年も昔、IBM社は「コンピュータは個々人の生産性の差を15倍以上に広げる」と予測しました。
生成AIなどを扱っていると、近未来には、その差は100倍以上になることが実感されます。
1人の会社が100人の会社と同等の生産性を有したら、これは勝負になりませんね。
そこまでいかなくとも、すでに10倍に達している例は出ていると思います。
そうした中で、「全従業員一律5%のベースアップを・・」などを掲げる春闘のばかばかしさを感じる方(特に若者)は多くなっていると思うのです。
ただし、企業がたった1日で10倍の生産性を上げることは不可能です。
そのための投資と人員の再配置、業務の劇的改革が必要だからです。
しかも、その投資には利益を上げる目標と道筋の整備が必要です。
このことが企業に投資を躊躇させる難しさになっています。
私の会社でも、利益目標なき投資を進言してきた営業幹部がいました。
私が「この投資で、いくらの利益増進を見込むのかね」と聞いたところ、彼は「やってみなければ分かりません」との答え。
私が「それは分かるよ。だから、ノルマではなく利益の増進目標を聞いているんだよ」と言っても、頑として「やってみなければ分かりません」を繰り返すのみ。
たとえ、結果が出なくても原因を総括した上で、再挑戦することを期待したのですが、「やってみなければ・・」に固執するばかり。
期待していたのですが、がっかりでした。
ただ、それだけ投資責任を負うことが社員にとっては大きな重荷なのです。
サラリーマン時代を振り返ってみれば、自分が進言した投資が失敗した場合、クビにはならないまでも出世の道は絶たれた可能性が高かったかと思います。
だから「やってみなければ・・」の社員の気持ちはよく分かります。
ですが、そうした計画無き投資は、企業を弱める結果となりかねません。
企業が生存するための“コメ”である資金を使う以上、いい加減な投資を許可することはできません。
次回は、そのことを論じたいと思います。