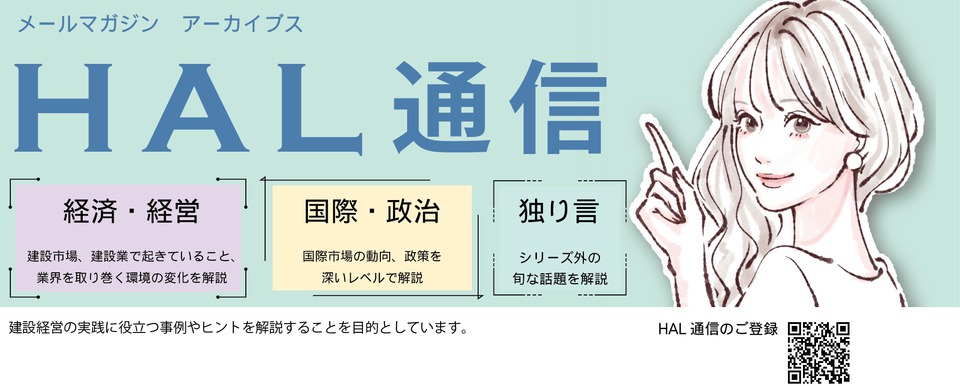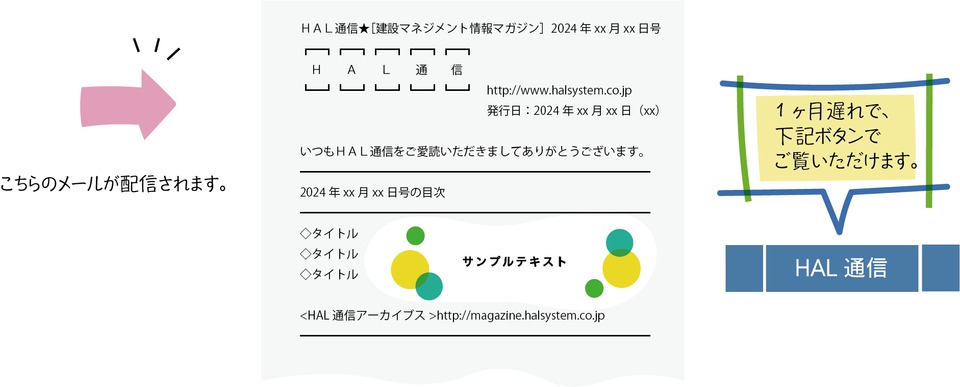新車陸送の世界(4)
2025.08.01
日産自動車が、2027年度末までに追浜工場を閉鎖することを発表しました。
この工場は、若かった私が、座間工場の次に輸出用の新車を多く本牧埠頭まで運んだ工場です。
座間はとうの昔に閉鎖され、そして追浜かと思うと“何とも言えない”寂しさを感じました。
では、ここから、その過去にタイムスリップします。
陸送2日目は、その追浜工場からの新車陸送でした。
追浜は、他工場より横浜・本牧埠頭に近いので、夕方の陽の光が残る時間に私は最初の輸送で埠頭に着きました。
そして、埠頭の光景に目を見張りました。
昨日の最後の輸送(つまり当日の明け方)、最後の車を運び終えた時、広い埠頭は想像もつかない数の車で埋め尽くされていました。
それが、1台残らず消えていたのです。
あの膨大な数の車は、昼間のうちに全て船積みされ、出航されていたのです。
我々のチームが最初に埠頭に着いたので、広大な埠頭には1台の車もなかったのです。
本牧埠頭の面積は、287.7haあります。
1haは1万平方メートルで、坪数だと3025坪です。
50坪平均の住宅地だと道路部分を除いて、50区画ぐらいとなるでしょうか。
つまり、本牧埠頭に住宅街を作るとすると、1万区画以上の住宅が立ち並ぶ広大な街となる計算です。
気が遠くなる面積ですね。
そこを文字通り“びっしり”と埋め尽くしていた車が、たった1日で1台残らず無くなっていたのです。
あの当時、そうした光景が休みなく毎日繰り返されていたわけです。
それも本牧埠頭だけでなく、日本の多くの港においてです。
考えただけでめまいがしてきます。
その光景の延長線上に、今日の日米自動車摩擦があるわけです。
我々は、その先兵だったのです。
この日、埠頭から工場に戻るマイクロバスの中で、一人の先輩が、こんなことを私に聞きました。
「おまえ、アクセルは何のためにあるか、知っているか?」
私は困惑しながら、「車を走らせるためです」と答えました。
先輩は、面白そうにニヤッと笑い、
「違うな、アクセルはな・・床まで目いっぱい踏み込むためにあるんだよ」
こうした新米いじりは、先輩方の楽しみのようで、全員ニヤニヤしながら、こうした“やり取り”を聞いていました。
しかし、この答えは冗談ではないのです。
全員が、本当にアクセルを床まで踏みつけ、夜の国道を全速力で駆け抜けていたのです。
当時の車でも時速150~160km以上に達していました。
その速度で、制限50~60km/hの一般国道を、信号を無視して走っていたのです。
さすがに横浜市内に入ると夜でも交通量が増えるので、そんな運転はできません。
それでも100km/hぐらいの速度で、他の車を追い抜き、かわしながら突っ走りました。
輸出する車のタイヤは空気圧を目いっぱい高くしてあります。
船で輸送する間に徐々に空気が抜けるからです。
ですから、ハンドル操作が異常に軽くなり、少しでもオーバー気味に切ると思わぬ方向にすっ飛んだり大きくスピンしたりするので命がけです。
この高い空気圧で突っ走る雨の日の道路は、スケート場と化します。
カーブはすべて4輪ドリフトで大きく横滑りしながら曲がります。
レース場のほうが安全なくらいです。
ですが、当時の私に“危ない”という意識はなく、「レースの訓練だ」との意識で運転していました。
これも若さという「バカさ」のせいですね。
年を取った今の私から見ると、まったくの別人です。
当時の私は、陸送のバイトとは別に、レーシングチームのメカニックを手伝っていました。
そのレーシングチームは自動車会社がスポンサーの、日本でもトップクラスのチームでした。
そして、そこには4人の「エース」と呼ばれるドライバーがいました。
いずれもレースの世界では自動車雑誌を飾るほどの超有名人で我々の憧れの存在でした。
その中に、私と同じ新車陸送の世界からレーサーになった方がいました。
その方は、私が新車陸送のバイトをしていることを知って、なにかと声を掛けてくれ、ドライビングテクニックの指導もしてくれました。
その方が、ある日、こんな話をしてくれました。
「僕も新車陸送で腕を磨いたんだよ。でも間一髪が何回もあった。陸送車で公道を突っ走るのはレース場より危険だ。君はもう分かっているだろうが、命の大切さは忘れるな。そして、一般人を巻き込むことだけは何が何でも避けろ」
素晴らしい先輩でしたが、それから3年後、返らぬ人となってしまいました。
サーキットでの練習走行中の事故でしたが、原因は分からないままでした。
あの方の言葉と、あの事故当時の胸の痛みは今でも消えることがなく、思い出すと涙が出てきます。
その事故の少し前、もう一人のエースの方が、やはりレースの練習走行で命を落としました。
エース4名中2名の方が20代半ばで命を落としたのです。
当時のレース世界が、とんでもない世界であることがお分かりかと思います。