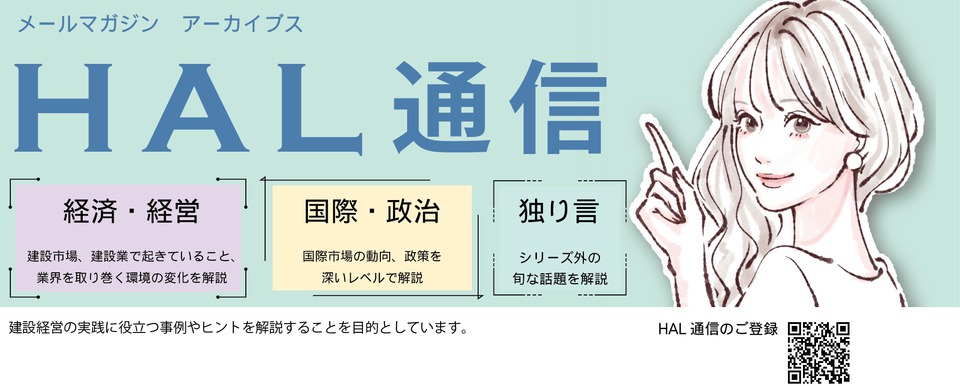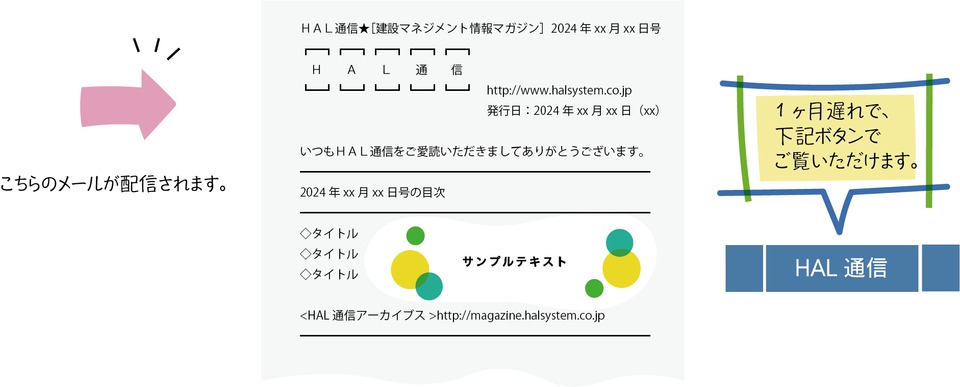企業の投資(5)企業収益が生み出す差額と内部留保
2025.11.04
企業とは、価値の低い原材料を仕入れ、その仕入れ価格の上に製品に仕上げる製造コスト、労働対価、企業を維持・発展させるために必要な管理経費、さらに欲しい利益額を乗せた売価で販売し、それらの差額を蓄積していく「装置」です。
企業の投資原資として最も好ましいのは、こうした差額の蓄積です。
もちろん、差額が溜まるのを待っていられないケースが多いので、「投資は借入で」が普通に行われています。
でも、その借入の返済原資も、この「装置」から生み出される“差額”です。
このように「企業は装置」と言い切ると、非常に無機質な存在のように見えてしまいます。
また、正当な方法で高い収益を上げる経済モデルは“美しい”と評されることがありますが、その裏には精緻な数式が高度な整合性を持って“冷たく”存在しています。
こうした「美しさと冷たさの両面を高度に保つ」企業が“優れた企業”と言われます。
ただし、こうした整合性が常に保たれる保証はありません。
大きな景気変動、今回のトランプ関税のような外圧、法改正、事故など、整合性を狂わせる要素には事欠きません。
こうした中で企業が生き延びていくため、生身の人間である従業員の尊厳や暮らし、あるいは社会の安定がある程度犠牲にされていくのは、資本主義の、いや大きな意味での経済活動の必然といえます。
このような資本主義の非人間性を批判して計画重視の社会主義、その発展形の共産主義が生まれたわけです。
しかし人間性を重視したはずの計画経済は、結果として歯止めの効かない独裁体制になり、破綻するか破滅の道へ向かったことは近代の歴史が証明しています。
誰もが名前を聞いたことがあるピーター・ドラッカーは近代経済学の父ともいえる存在です。
彼が、自分のことを「社会生態学者」と呼んでいたのは有名な話ですが、こうした不安定さを抱えている経済はあくまでも人間社会という“生態系”の一部であり、社会全体の健全性に貢献して初めて意味を持つと考えたのです。
彼は、人間や社会をその生きるための土台から切り離し、経済自体が自己目的化してしまうシステムの危うさに警鐘を鳴らしていました。
AIシステムに無自覚に傾こうとしている近年の企業経営に対する警告とも言えます。
彼は2005年11月にこの世を去っていますので、現代のAIブームは知らなかったわけです。
それでも、その危険性を見据えていた慧眼には感嘆するばかりです。
さて、ここで企業収益というものを考えてみたいと思います。
「何を今さら・・」と思わずに聞いてください。
昨今のマスコミは企業が内部留保を貯め込むことに批判的で、経済評論家の中にも同じ論調で企業を批判する方が結構います。
そうした意見に同調する人々に言いたいことがあります。
企業収益を100%労働者に還元したのでは、企業の新しい明日が創れないし、不況になればあっさり倒産となってしまいます。
そうしたことに備えるため、企業収益の一部分を「内部留保」として貯めているのであり、外野がとやかく批判することではありません。
「いや、過剰に内部留保を貯め込んでいることが“けしからん”」と言われる方に言いたいです。
内部留保の多さは企業の株価に反映します。
その分け前が欲しければ、その企業の株式を保有すれば良いのです。
当然、配当は銀行預金よりは良いはずです。
批判するのではなく、考え、そして行動することです。
企業経営は、個人とは比べものにならない“果てしない”思考と行動の連続です。
内部留保は、貯め込むことが目的ではなく、次の投資原資として使うことで、その何倍もの収益を上げることが目的です。
次回に続けます。