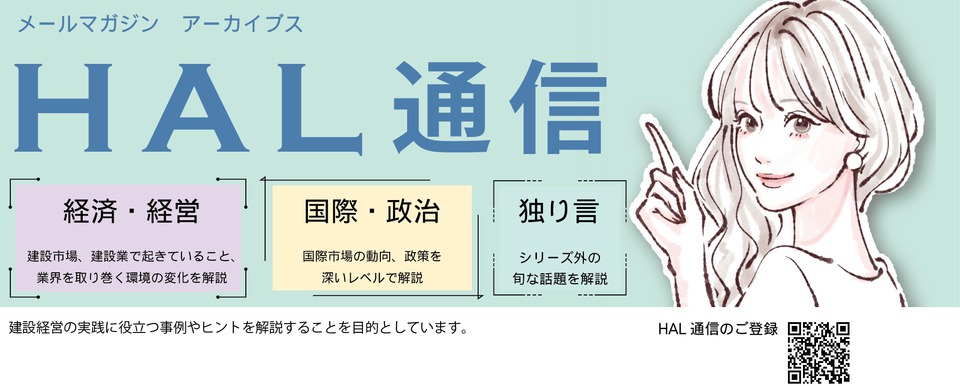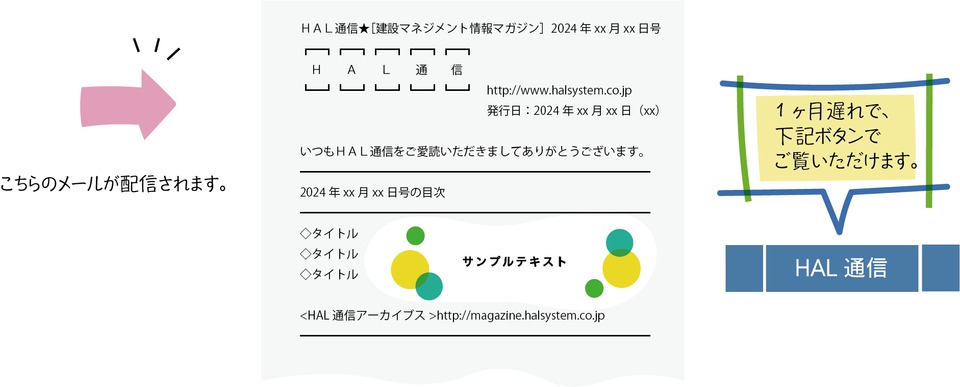企業の投資(4):投資と投機の違い
2025.10.01
米国企業が、自社株買いのための借り入れを大幅に増やしています。
企業が自社株買いを行うと、当然、その分の現預金高が減ります。
その欠損を穴埋めするため借入が増えているわけです。
日本でも、2023年に東京証券取引所が上場企業へ「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」を要請したことをきっかけにして、自社株買いが増えています。
企業が市場から自社株を買い上げれば、その分だけ市場における株式数が減り、株価は上昇します。
つまり自社株買いは、株主への還元になるわけです。
2025年4月、トランプ政権が関税政策の発動を実施したことで日米とも株価は急落しました。
その結果、自社株買いが急激に増え、その勢いは現在も続いている状況です。
もちろん、そのことで日米とも株価は持ち直しましたが、その後も自社株買いが止まらないことで株価は上がり続けているわけです。
これが最近の株価上昇の要因です。
大量の自社株買いが可能なのは、企業の現預金高が贅沢にあるからです。
この傾向は、特に日本において顕著です。
もともと日本企業は欧米企業に比べて保有する現預金高はかなり高い水準にあります。
2015年の「現預金高/純資産」を見ると、米国10%、欧州6.5%に対して日本は15%と、以前から多かったのですが、2022年には米国11.5%、欧州12%に対し、日本は24%と大幅に上昇しました。
2024年に若干下がりましたが、それでも米国12%、欧州10%、日本22.5%と相変わらず高水準です。
もちろん、この現預金高には金融機関からの借り入れが含まれます。
日本は記録的な低金利状態にあるので、借入を増やして自社株を買う動きがさかんになっていることが分かります。
日本より金利が高い米国でもこの動きは顕著で、それが株価上昇をもたらし、大株主の資産をさらに押し上げる要因になっているわけです。
このように、日米とも実質的に「当期利益<株主配当」となっている現状は健全な経営状態とは言い難い状況なのです。
本来、企業は「魅力ある商品やサービスの開発」に投資を行い、そこから生み出される利益の中から株主配当を行うべきです。
しかし、現在の自社株買いは投資ではなく、「投機」の範疇に入る資金の使い方です。
このように資金が投資に回らず、投機に回っている現状の行き着く先は、本来の企業活動である商品開発や販売が先細りとなり、カネだけが価値を持つ世界です。
そして、金融機関や投資家だけが儲かる“カネ余り”経済となり、やがてバブルを生み、弾け、そして不況が来るのです。
そうした暗い予想に危険を感じた経営層から「企業が長期的に成長するためには、ESGが大事だ」とする考えが米国で生まれています。
ESGとは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の頭文字を取った言葉で、これら3つの観点が経営において重要であるという考え方です。
以下のような説明がされています。
E(環境): 気候変動、温室効果ガス排出、廃棄物管理、汚染など、組織が環境に与える影響や環境管理者としての活動を指す。
S(社会): 多様性、包括性、人権、サプライチェーンがもたらす社会的影響など、組織が人、文化、コミュニティーに与える影響を指す。
G(ガバナンス): 役員報酬、後継者計画、取締役会管理慣行、株主の権利など、組織の運営方法や企業統治の要因を指す。
「国際問題、政治問題」の「トランプ対DEI」で解説したDEIはDiversity(多様性), Equity(公平性), Inclusion(包括性)の頭文字をとった言葉ですが、似ていて混同しますね。
DEIは政治的なメッセージで、ESGは投資活動に関する概念です。
ゆえに、DEIを執拗に攻撃するトランプ大統領も、ESGには“今のところ”何も言いません。
米国においては、企業の財務状況だけでなく、「ESG投資」の投資額が注目されています。
ESGに配慮する「ESG経営」という言葉も広まっており、投資に限らず企業の社会的な責任を示す指標にもなっています。
日本ではまだまだで、特に中小企業は、そのことに考慮する余裕もないでしょう。
しかし、自社が成長を目指すなら勿論、ESGに配慮する取引先企業が増えてくるなら無関心ではいられません。
純粋に利益を上げるための投資に加えて、ESG投資も考えていく必要があります。
<追記>
ESGと関連するキーワードとして、SDGs(持続可能な開発目標)があります。
SDGsが「目標」であるのに対し、ESGはそれを「達成するための手段」としての意味合いが強いとされています。